日本人の考え方 「和をもって貴しとなす」

ちょっと前まで誰でも「和をもって貴しとなす」を知っていたました。聖徳太子が言った言葉です。聖徳太子もみんなが知っている人物です。ただ今のZ世代とよばれる若者たちが知っているか、と言われると少し自信が無くなります。でも日本人には「和」を大切にする心が脈々と引き継がれているのは間違いありません。
すみませんの文化
外国から日本にやってきた人は、日本人がよく謝ること、よく譲りあうことに驚くかもしれません。
「すみません」(すみません)レストランで注文するときです。
「すみません」(すみません)お店で商品を買うときもです。
どう見ても謝る状況ではないのに「すみません」と謝ります。この言葉は街中で聞こえてきます。幼稚園の前で若いお母さんたちがお辞儀をしながらお互いに言っています。
「すみません」(すみません)
「いえいえこちらこそすみません」(いえいえこちらこそすみません)
かと思えば、別の場所ではサラリーマンが、手を差し出して何かを譲りあっています。
「どうぞ、どうぞ」「そちらこそ、お先にどうぞ」(どうぞ、どうぞ)(そちらこそ、お先にどうぞ)
これは日本で見られる日常風景です。
日本では「すみませんは」魔法の言葉です。どのように話しかけたら良いかわからないときは、この言葉を使っておけば間違いありません。このときの「すみません」は相手に手間を取らせることへの謝意を現します。
「すみません」はもとは謝罪の言葉です。「済む」という動詞に打消しの助動詞「ぬ」がついて「すまぬ」になり、その丁寧語の「すみませぬ」が「すまない」に変化して謝罪の意味を持つようになりました。明治時代から使われ出しその後に呼びかけや謝意を表す言葉になりました。
日本人はこの謝罪の言葉を頻繁に使います。失敗をしたときや自分が間違っていると思ったとき、小さい子供は別ですが、大人は直ぐにすみませんと謝ります。謝ると自分が不利になるとは考えません。間違っていたら謝ります。自分が謝ることで争いが起こるのを防ぐのです。その場の平穏を重視するのです。外国人は「自分を守ろうとしない考え方」を理解するのが難しいかもしれません。
議論をしても相手を論破するのは苦手です。自分の意見を押し通すより全員の意見を纏めます。それは不可能だと思えますが、みんなが自分の意見を修正するので時間はかかりますが最後は纏まるのです。外国人から見ればなんと非効率なことをしているのかと思うでしょうがそれが日本流なのです。この行動の元になるのが「和をもって貴しとなす」の考えです。

和をもって貴しとなす
日本の歴史は紀元前6世紀頃に始まります。聖徳太子は、それから1200年ほどたった7世紀の始めに、第31代用明天皇の第2王子として生まれました。成長すると摂政として政治を行います。太子は8人の話を一度に聞きながら、案件を処理できる天才だったそうです。厩戸皇子(うまやどのおうじ)と呼ばれたのでイエス・キリストと関係があるのでは、と言われましたがさすがにそれはないようです。
聖徳太子は人が守るべき道徳的な戒めを17条憲法として定めました。「和をもって貴しとなす」はその第一条にあります。太子が言う「和」は人と人が争わず仲良くすることです。ただ、自分の気持ちを無理に抑えたり、相手の気持ちを無視することではありません。上辺だけ仲良くすることでもありません。他人を尊重したうえで協調することです。
日本人は、太子の教えを14世紀の間、律儀に守ってきました。小国に分かれて争った戦国時代でさえ教えを大切にしました。戦国時代の武将は、戦って全てを得るより戦いを避けて損失を減らすのが得策と考えました。我慢の限界を超えると負け戦と分かっても戦う過激さがありましたが、原則は譲れる条件なら戦いを回避しました。「和」の教えに従おうとしたのです。

京都のぶぶ漬け
そのように和を重視する社会でも、人が人である限り、主流の考えと異なった主張をする人はいます。和を乱す人は出てきます。そういう時はどうするのか。それを説明する前に、日本の古都である京都の「京都のぶぶ漬け」の話を紹介したいと思います。
ある人が京都の旧家を訪問します。話がはずみ時間がどんどん経っていきます。
旧家の主人が言いました。ぶぶ漬けとはお茶漬けのことです。
「だいぶ遅くなりました。ぶぶ漬けでもどうですか」(だいぶ遅くなりました。ぶぶ漬けでもどうですか)
言われた客は慌てて席を立ちました。
「あぁ、もうこんな時間ですか。失礼しました」(あぁ、もうこんな時間ですか。失礼しました)
このお話が理解できますか。
「ありがとうございます。頂きます」(ありがとうございます。頂きます)
普通だったらこう言いますよね。
でもこの「ぶぶ漬け」は主人の「そろそろお帰り下さい」との意思表示なのです。京都には相手が気分を害さないように要求を非常に婉曲に伝える習慣があります。
今は流石にこんな極端な例ありません。「京都のぶぶ漬け」は、京都人の閉鎖性や嫌味さの象徴として面白可笑しく語られるだけす。京都だけでなく日本には「そろそろお帰り下さい」でなく「良い時間になりましたね」という風に婉曲に伝える傾向があります。婉曲に伝える能力とそれを察する能力が必要です。日本はなかなか難しい社会です。

和を乱す者は静かに排除される
それでは和を乱す人にどう対処するのでしょう。まずその人に婉曲的な表現で「和を乱している」とのメッセージが伝えられます。「あなたは間違っている」と直接的に言われるのは稀です。それが何度か続いてても状況が変わらなければ、どうなるか。和を乱す人の周囲から集団のメンバーが居なくなります。仲間外れにされるのです。
その人と争わずに静かに排除します。これは怖いですね。それに陰湿です。外国人が和を乱す感覚や排除の基準を理解するのはとても難しいことです。日本が排他的で冷たいと思われる所以です。
それもそのはず日本人でも排除の理由が分からないときがあります。排除される人に、和を乱している意識がないときや、伝えられたメッセージが理解できないことがあります。排除する側の人も、排除の理由がなんとなく共有された雰囲気なので、明確に伝えるが難しいことがあります。「あなたのここが間違っている」と言えば良いのですが、争いを避ける意識が強いので言いません。排除側も排除される側も何が問題か分からないまま進んでいく。悲劇です。
この争うこと無く集団の秩序を守る方法は長い歴史から生まれました。同じ意識を共有する者だけが理解できる方法です。第3者には分かり難い、何とも陰険で意地悪な方法です。和の文化の暗黒面と言えるでしょう。ですがこの暗黒のパワーが発揮されることはめったにありません。日本の文化や習慣、ルールを守り攻撃的にならなければ大丈夫です。

和の教えは、単一の王朝、ほぼ同じ民族、大部分が仏教徒、島国なので異民族の侵攻が殆どなかった、水が豊富だったので徹底的に争う必要がなかったという条件が揃って、維持できた世界でも稀な考え方です。
現代でも、日本人はよく謝り、よく譲り争いを避けます。「すみません」「どうぞ」「お先に」などの言葉が街中に溢れています。人を罵る大声や口論、けたたましいクラクションの音は聞こえません(最近は少し変わってきているようですが)譲りあうので最小限のクラクションで良いのです。「和をもって貴しとなす」の精神は静かで穏やか社会を作っています。
日本人はどうしてすぐに謝るのか、どうして自己主張をしないのか、と不思議に思ったら「和をもって貴し」を思い出してください。日本人は自分が損をしても社会が得をする生き方を選んでいます。争わないことが最優先です。弱々しい生き方に見えるかもしれませんが、平和を守るには良い考えだと思いませんか。
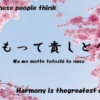
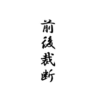




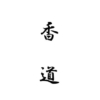
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません