母の日 母が好きでない花を贈っても贈らないよりは数倍良い
今年は桜の花の上に雪が積もるという奇妙な春だが、満開になるとすぐに新緑の季節がやってくる。爽やかな新緑が風に揺れる頃、母の日がやってくる。なんとまぁ気の早いことだと油断しているともうその日である。慌ただしい季節だけれど日頃忘れがちな母へ感謝の気持ちを贈りたい。

目が見えなくてもいいのだけれど、一度だけ目が見えたら母の顔をみたい
母へのせつない想いを表現した美しい言葉だ。盲目のピアニスト辻井伸行さんの言葉である。とても大切に思っているのについ忘れてしまうのが母である。コロナのために会えない日が続いた。コロナが終わり自由に会える日がきても事情があって母に会えない人も多い。
今年も会えないかもしれないので花を贈りたい、いつも会っているけど特別の日だから花を贈りたい、と思っているうちに母の日が過ぎてしまった。大抵の男はそんなことの繰り返しではないだろうか。
・花を贈りたいが、どこに頼めば良いかわらない。
・毎年カーネーションを贈っているけど、今年は違うの花を贈りたい。
・どのような花が良いか悩んでしまう。
母の日の由来
母の日は米国のバージニア州から始まった。南北戦争のさなか、アン・ジャービスさんという女性が、敵味方に関係なく負傷兵の衛生状態を改善しようと活動した。彼女が亡くなった後、娘であるアンナ・ジャービスさんは母の功績を偲ぶ記念会を開催したいと考えた。
1907年5月12日、その願いは母が日曜学校の教師をしていた教会でかなう。彼女は集まってくれた人に生前母が好きだった白いカーネーションを配った。彼女の母を思う気持ちは多くの人達に伝わり、5月12日を母の日として祝うようになる。1914年に米国の正式な記念日となり、5月の第2日曜日と正式に定められた。女性たちの優しさが政府を動かしたのである。
アイルランドとイギリスは17世紀からマザリングサンディがあった。当時子供たちは幼くして働きに出た。その子供たちが教会で母に会える日だ。オーストラリアの母の日は、シャトル・ヘイリンさんが、老人ホームで過ごす寂しい「忘れられた母達」を癒そうとクリサンセマム(菊)を贈ったことに始まる。その日が母の日になった。
日本でもかつて薮入という習慣があった。旧暦1月15日(小正月)と旧暦7月15日(盆)は奉公に出た子供や嫁いだ娘が実家に帰れる日である。母に甘えられる数少ない日だった。母に会いたい気持ちは洋の東西を問わない。
今のような母の日が日本で始まったのは1949年である。米国に倣って始まった。母が健在であれば赤いカーネーション、亡くなっていれば白いカーネーションを贈った。その後赤いカーネーションが一般的になった。

母の好きな花を知っていますか
花を贈るなら由来からカーネーションが無難だけれど、他にも綺麗な花がいっぱいある。その花の中から贈る花を選びたい。だが男はどれを選んで良いかわからない、そんなときは母が好きだった花を思い出してみよう。
幼い頃いっしょに眺めた花、母が育てていた花、母が撮った花の写真、テーブルにいつも置かれていた花、記憶のなかにヒントがある。年に1回のことだから一生懸命思い出そう。思い出をたどるのは悪くないはずである。
・母の好きな花を思い出す。
・楽しい思い出をメッセージにする。
・花を育てるのが好きな母には鉢植えも良い。
花言葉と本数に気をつける
母と言えばサトウハチローの詩が美しい。詩に良く出てくる花が紫陽花(あじさい)である。そのため母のイメージが強い花だが、花言葉は「移り気」「浮気」「無常」と母に贈るのはふさわしくないように思える。そこは良くしたものでピンクの花だけ花言葉が「元気な女性」になる。だからピンクの紫陽花は母の日の贈り物として人気がある。みんなが好きな花には良い言葉がある、花言葉は良くできている。
・「嫉妬」や「孤独」は避ける。
・色によっても花言葉は異なるのでよく調べる。
・4本や9本、13本は、気にする人がいるので避ける。
母が好きでない花を贈っても、贈らないよりは数倍良い
考えてもどうしても母の好きな花が思いだせない、決まらない、考えるのが面倒臭くなった時は唯我独尊で自分の好きな花を贈ろう。間違って母が嫌いな花を贈っても、贈らないよりは数倍良い。
・遺伝子の半分は母、好みは似ているはず。
・潜在意識に子供時代の記憶があるはず。
・孫が選んだ花に勝てる母はいない。

子供が口にしないことでも母親は理解している
ユダヤの諺にある。母は子供がなぜその花を選んだかをわかってくれる。どんな花を貰っても贈られても嬉しい。照れくさいので文句は言うかもしれないがたとえ野に咲く一本の花でも嬉しいのだ。それでも決まらなかったら、花は諦めてスィーツや果物にしよう。一緒に食べればさらに喜ばれる。


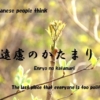

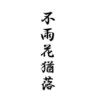
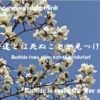
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません