本 「その日暮らしの人類学」その日暮らしという生き方
タンザニアの人たちは、小規模な商売で生計を立て困ったときは友人に金を借りて前へ前へと進んでいく。「その日暮らしの人類学」はその社会のフィールドワークから生まれた。そこには日本人とまったく異なる生き方がある。
日本の若者たちは終身雇用や年金制度の崩壊に怯えて絶望しているが(無理ゲー社会)、彼ら物質的な豊かさに恵まれなくても精神的に豊かに生きている。未来は、彼らにとって心配する対象でなく何かを始めるチャンスである。

Living for Today 今しか考えない人達
話はピタハンというアマゾンに暮らす種族から始まる。彼らは現在を表す言葉しか持たない。過去や未来を表現する単語が無い。過去がこうだったからこうしようとか、明日のために準備するという概念が存在しない。現在のみに生きている。
アフリカに住む農耕民族トングウェ人はできるだけ少ない努力で暮らそうとする。将来に起きることは起こったときに考えれば良い。農業はするが作物は最小限を育て蓄えは持たない。彼らはその日暮らしの人たちである。タンザニアの若者は仕事は仕事と割り切り職業を気軽に変える。お金に困ったら知人に金を借りる。自分にお金があれば他人に貸す。貸した借りたで毎日を過ごす。
日本人は将来の心配ばかりしている。そんな考え方は世界で少数である。世界の大半はその日暮らし人たちである。そんなアフリカ人が中国との間に大きなグローバル経済圏を作っている。その日暮らしとグローバル経済がどのように繋がるのか。筆者は日本人の知らない社会と生き方をいきいきと描いている。
目次
Living for Todayの人類学に向けて
第1章 究極のLiving for Todayを探して
第2章 「仕事は仕事」の都市世界 インフォーマル経済のダイナミズム
第3章 「試しにやってみるか」が切り開く経済のダイナミズム
第4章 下からのグローバル化ともう一つの資本主義経済
第5章 コピー商品/偽物商品の生産と消費にみるLiving for Today
第6章 仮をまわすしくみと海賊的システム
Living for Todayと人類社会の新たな可能性
同著

その日暮らしの経済と心の豊かさ
目標や職業的アイデンティティを持たず、浮遊・漂流する生き方は、わたしたちにはいきづらいようにみえる。だが、「カネがない」の意味で「困難な人生」と語られることは多くても、前へ前への生き方に特別な不安感や空疎さを重ねる言葉をほとんど聞いたことがない。
「その日暮らし」の人類学 もう一つの資本主義経済
タンザニアの若者は常に前へ前へ進む。金が貯まれば新しい商売を始める、商売が上手くいけばノウハウを他人に簡単に教える。そうすると大勢がその商売に殺到して儲からなくなるがノウハウを隠そうとは考えない。頼まれると商売の元手として溜めた金も優先して貸してしまう。
みんながそうなので、お金は貸したり借りたりで仲間の間をグルグル回って暮らしていける。彼らはお金を借りるより貸した金を督促するのに罪悪感を感じる。
小さな商売はインフォーマル経済と呼ばれて遠く中国まで繋がってる。中国で商品を仕入れてアフリカで売る。一つの商売は小さいが、多くの商売が集まって「下からのグローバル化」と言われる巨大な経済規模になっている。商品はコピー品や粗悪品、知的財産権を無視した製品など何でもありだ。アフリカの市場は安かろう悪かろうで良いのである。タンザニアの若者はそんな商品を売りながら毎日を生きている。
海外旅行はJTB!Web限定商品など、海外ツアー検索・予約が可能!
タンザニアの殺到する経済、インフォーマル経済のダイナミズム
インフォーマル経済は、日本では知られていないが、アフリカと中国を包括する大きな経済圏である。個人が勝手にはする商売だからインフォーマル経済と呼ばれる。誰かが商売を始めて、ネズミが歩くような細い道ができると、あっという間に拡大してゾウの道のように広くなる。インフォーマル経済自体が今やゾウの道である。
この経済は2000年代中国が世界の製造工場になった頃から急速に拡大した。世界経済に占める割合が30%になろうとしている。ただ拡大しても個人対個人の少額取引の形態は変わらない。個人の信用取引である。詐欺にあっても騙されたても、騙された方が悪いの世界だ。そこには「法律には違反するかもしれないが、社会的には認められる」という暗黙のルールだけがある。アフリカ人と中国人はその生き馬の目を抜くような世界で商売をしている。
筆者の小川さやか氏は、アフリカ東部(主にタンザニア)と香港や広州をフィールドに「Living for Today 」と、「 Informal economy」を調査研究をしている。タンザニア人の人生観、中国人の知的財産権を無視する意識、アフリカと中国の親和性をわかりやすく説明している。

アフリカと中国のインフォーマル経済
アフリカの商人は、香港を窓口にして広州や深圳ヘ向かう。広州は、昔シンドバットが住んでいたが、今はアフリカ人が住んでいる。求めるのは中国企業が作る小ロットで廉価な製品である。中国企業はコピー品や廉価品、携帯電話など何でも作ってしまう。中国企業は山賊のように法律を守らない。そんな集団だから山塞企業と言われる。山塞とは山賊の要塞のことだ。
彼らは、西欧的な知的財産権、契約書、品質保証や品質管理は無視である。そのかわりにダイナミックな開発力と価格競争力を持ち短期間で何でも作ってしまう。基本的に「安かろう悪かろう」だが、アフリカやアジアではそれで十分なのだ。「金はないが直ぐに欲しい」「ちょっとの間使えれば良い、高品質はいらない」それが市場のニーズである。「安物買いの銭失い」の日本人には理解しにくい感覚である。
日本でインフォーマル経済が報道されることはほとんどない。日本人は中国経済の強さやの本質やアフリカの購買動機を理解するのが難しい。チョンキンマンション、ムーンライト企業、リアルコピーなどこ聞き慣れない言葉の意味を知るとインフォーマル経済の実態が良くわかる。中国と東アフリカは昔から強く結び着いている。中国政府とアフリカ各国の交流が話題になるが、古い庶民の草の根の交流がその土台にある。中国政府の経済援助だけで成り立っているという考えは皮相的すぎるのである。
チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学
日本人が知るべき「その日暮らし」の価値感
誰でもいいから助けてくれないかと、アドレスの順に沿って電話する。毎日のように金を送り合っているので、たまに誰からいくら借りてだれにいくら貸しているのか混乱する、ただ、その時々に金を持っていた誰かが食い扶持をくれたことに変わりがない。自分だって金があるときそうしている。
キオスク店主 20代なかば 同著
タンザニアの「その日暮らしの生活」は気軽な貸し借りで成り立たっている。借りるのも貸すのも当然だ。哲学者ナタリー・サルトゥー=ラジュやマルセル・モースは、共同体は貸し借りの概念が重要という。日本は他人に物を借りるのは恥とする。いつも他人に迷惑をかけないように生きている。職場では生産性向上や高品質を考え家に帰れば老後の心配をする。将来のお金を貯めるために今を犠牲にするのは当然と教えられる。イソップ物語の「アリとキリギリス」のアリの立場である。
ビル・パーキンスは著書「DIE WITH ZERO」で問いかける、アリはいつ遊ぶことができるのだろう。日本人はいつ楽しむのだろうか。日本は、技術が発達して豊かになったが、その結果に追い詰められている。ちょっと昔まで、日本もタンザニアのようにお米や醤油の貸し借りがあった。そんな共同体で暮らしていた。
「その日の暮らしで生きていく」社会は世界中にある。物質的には貧しいけれど幸せがある。タンザニア人は仕事に縛られず友人と携帯電話があれば十分だ。日本人から見ればなんとも自由な生活である。タンザニア人や中国人の生き方を知れば、少しは発想が変わるのではないだろうか。毎日が息苦しい人、中国とアフリカの経済関係に興味のある人にお勧めの一冊。




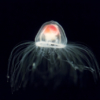

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません