日本人の考え方 中国文化と現代中国
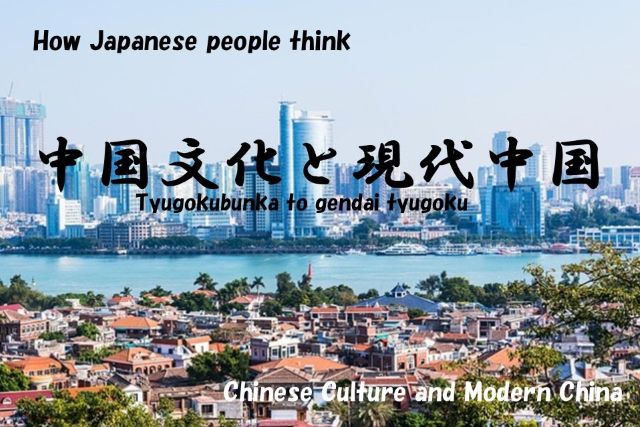
最近の日本と中国の関係は少々微妙です。日本人は自分たちは常に正しいと主張する中国政府の仏頂面の報道官や、日本に住みながら社会のルールを守らない中国の人達が好きではありません。街でゴミを捨てたり大声で話すのも嫌いです。それでも日本人は中国の歴史や文化が大好きで尊敬しています。

日本人小説家は中国の物語を書く
日本人は遣隋使や遣唐使が持ち帰った文化や制度で日本国が設計されたことをよく知っています。漢字も「漢の字」として中国から学んだことを表しています。「そんな歴史は無い、中国には何も学んでいない」と言う人はいません。それどころか中国の歴史が大好きなのです。日本の小説家は中国の物語をたくさん書いています。吉川英二は三国志や水滸伝を日本語に書き直しました。司馬遼太郎の中国旅行の紀行文は秀逸です。彼の項羽と劉邦はベストセラーになりました。
宮城谷昌光も公孫龍を書いています。伝奇小説で有名な夢枕爆の作品にも中国を舞台にした空海があります。田中芳樹の創竜伝も中国大好きの小説の一つでしょう。漫画でも流行中の原泰久のキングダム、諸星大二郎の諸怪志異や西遊妖猿伝は面白い。薬屋の独り言も中国風です。
個人的に好きなのは吉川英二の水滸伝です。花和尚魯智深や黒旋風李逵の傍若無人の暴れっぷり、紳士とされる豹子頭林中や大人と尊敬される及時雨宋行だって人を殺します。武松の酔っ払っての虎退治や九紋龍の史進が山賊との友情の為に村を捨てる話も痛快です。しかしですよ、この英雄たちの日常生活は日本の基準でいったらもう無茶苦茶です。
魯智深は寺にいながら酒は飲むし喧嘩はする。破落戸を集めて周囲に迷惑ばかりかけている。李逵だって料亭に良い魚が無いと大暴れする。最後は梁山泊に集まって反政府組織になる。水滸伝側の人は良いですがそうでない人はたまったもんじゃない。敵役の高俅や役人も権力を傘にきて極悪非道の政治をするからお相子ですが。

中国の古典が大好き
歴史以外でも中華料理やショートドラマは人気が高い。禅語や故事成語にまつわる物語が好きな人は多い。それらは日本のなかにしっかりと根づいています。例えば「完璧」です。この言葉は中国の戦国時代の故事に由来します。それと知らない人でも当たり前のように使います。二時間ドラマ「天才外科医、鳩村周五郎」の主人公、鳩村の手術が成功したときの決めセリフは「完璧の璧(カンペキノペキ)」です。若い人も何かが上手くできたときは「完璧」と言います。英語の「パーフェクト」ですね。
「壁」とは中国人が好む玉のことです。この玉は野球やサッカーで使うボールではありません。「玉無し野郎」と罵られる男の股間にある物でもありません。この玉は「ギョク」と呼ばれる宝玉のことです。中国の人達は古来より半透明の柔らかい玉を愛しました。中央アジアの和田(ホータン)で採れる羊脂玉は特に珍重されました。そんな玉の故事から「完璧」が生まれました。
中国の春秋戦国の時代、楚の国に下和(べんか)という人がいました。彼は山中で良い原石を見つけたので楚の厲王に献上します。王が鑑定士に見せると雑石だと言う。王は怒って彼の左足を切る刑を与えます。彼は、厲王の没後、新王である武王に再び献上しますが同じ理由で残った右足も切られてしまいます。足を切る罰も凄いが再び献上する下和も凄い。さすが中国です。
卞和は、次の文王が即位すると石を抱いて3日3晩泣き続けます。文王がそれを訝しみ試しに原石を磨かせてみると素晴らしい玉でした。文王は先王の不明を詫び、卞和を称えてその玉を「和氏の璧(かしのへき)」と名付けました。
「和氏の璧」はその後再び戦国時代の歴史に登場します。その頃「和氏の璧」は趙の恵文王の手にありました。秦の昭襄王はそれが欲しくてたまりません。彼は恵文王に秦の15の城と「和氏の壁」を交換にしようと持ちかけます。恵文王は璧を得るための陰謀と疑いますが、なにしろ秦は強国であり無下にできません。恵文王は悩みます。
それを見かねた臣下の藺相如は自分が秦に行って交渉すると奏上します。藺相如は秦に着くやいなや昭襄王に面会し本当に城を渡す気があるのか交渉を始めました。そのときの形相は「怒髪天を衝く」ものでした。彼は命をかけた交渉をして璧を国に戻す約束を得ました。史記「廉頗藺相如伝」の名場面です。昭襄王も藺相如の気骨を誉めて趙へ帰します。相如は任務を完全に完うしました。この故事から「完全に物事を成し遂げること」を「完璧」と言うようになりました。

日本社会に溶け込んだ故事成語
日本人はこういう故事成語が大好きです。舞台を日本に移し替えた話を創作します。中国明代の怪奇小説集「剪灯新話」にある「牡丹燈記」は娘の亡霊が若い男を取り殺す物語りです。これが日本で翻案されて「怪談牡丹燈籠」になりました。また鎌倉武士の心意気を示す「鉢の木」の謡曲も中国の故事からきています。鎌倉武士の佐野源右衛門は落ちぶれた生活を送っていました。そんな彼のところに一人の僧が宿を乞います。
彼は僧に暖を取らす為に囲炉裏に薪を足そうしますが薪がありません。僧は黙っています。源左衛門は大切に育てている、梅や松、桜の盆栽を薪にしました。僧は感服して聞きます。「あなたはどのような方ですか」「私は鎌倉武士です。こんな貧しい暮らしをしていますが馬と武具だけは残しています。いざ鎌倉の声がかかれば真っ先に駆け参じる気概は忘れておりませぬ」僧はもと執権の北条時頼でした。後に源左衛門を取り立てます。
この物語の元ネタは中国ですが強烈です。三国志の時代、劉備は呂布との戦に敗れ一人の猟師の家に落ち延びます。猟師は貧しく劉備に食べさせる食料がありません。彼は自分の妻を殺してその肉を料理してもてなします。劉備は感謝して色んな人にこの話を語ったそうです。料理にしたのは妻ではなく子供という説もあります。どちらにしても、なんとも凄いなと考えてしまいます。
中国は昔から強烈な専政政治の社会です。そこに異民族の侵入、度重なる戦乱、天災による飢饉などたいへん過酷な環境で多くの人は暮らしてきました。中国の古い教えに「吃苦」があります。「吃苦」とは痛みを全て飲み込むことです。中国の極貧の村に生まれたクリスティー・シェンはアメリカに渡って、この教えを実践して大金持ちになりFIREを実現しました(最強の早期リタイア術)
中国の農民は「吃苦」によって圧政に耐えてきました。ですから強い性格でないと生きていけません。日本人のように遠慮していたらあっという間に丸裸にされてお終いです。話は変わりますが、中国では万頭に使われる餡は肉が原料ですが、日本に渡ってくると餡の原料が小豆になりました。肉まんの肉餡も美味しいですが大福餅の小豆餡は優しい甘さです。中国の故事も食べ物も日本に渡ってくると優しく変化するようです。
日本は自然が豊かで水や食料を入手し易く、海に守られているので異民族の侵入が殆どありません。天皇は専制政治をしません。中国と反対の環境でした。それに加えて黒潮の乗って渡ってきた南洋の人達の遺伝子も入っている。色んな要素があってそこに住む人々の性格を穏やかにした。だから中国の過激な元ネタも優しく改良されました。

今、日本にやってくる中国の人達
中国社会はお互いが主張して妥協点を見出すことで成立しています。日本はお互いが遠慮する社会です。その穏やかな日本社会に主張の強い中国人が大量に入ってきた。それも急激にです。日本人は大いに困惑しました。中国は好きだけど現在やってくる人は我が強すぎて苦手だなが本音です。
ただ多くの日本人は、中国人が日本社会のルールを守ってくれれば受け入れられると思っています。実際、横浜や神戸の中華街の人達は日本社会に溶け込んでいます。彼らは、自国の文化を守りながらも日本に住んでいることを意識して日本の慣習を守ってきました。だから上手く行っているのです。
それが最近やって来る人達は中国と同じように暮そうとします。ゴミ出しや携帯のルールが守れない。日本人との軋轢が大きくなる。これでは上手くいきません。どうしてこうなったのか。昔の中国人と今の中国人は違うのか。人数が増えたせいか、豊かになった社会から来たせいか。それはわかりません。
でも日本人は中国が好きなのは変わりません。中国の人が少し日本社会を勉強してルールを守れば上手くいくでしょう。それと日本人も、中国の文化や故事成語の物語を読んで中国の人の気質を知れば、もっと上手く行くに違いありません。

結論のようなもの
現代の日本と中国の関係はお互いが慎重に握手をした結果によって成り立っています。その背後に深遠な歴史があります。日本人の魂は、中国の古典、哲学、そして歴史という糸で織り合わされているので、古代の中国文化にたいする敬意は永続するはずです。
現在の摩擦は、この深い文化的つながりを拒絶するものではなく、根本的に異なる二つの社会運営システムが突如として大規模に遭遇したことから生じた課題です。中国は積極的な個人の表現に基づき、日本は微妙な相互尊重に基づいて行動します。この二つが持続的な調和をするためには、複雑さを否定することではなくお互いの文化を認めることです。
つまり、双方が積極的に社会教育に取り組み、忍耐強く対応しながら共通の文化への尊重を育み続けることが必要です。深い歴史的つながりと現代の行動様式の違いを、意識的に乗り越える努力を続けることによってのみ、「近くて遠い」関係は真に協力的で敬意に満ちた関係へと発展できるのでしょう。


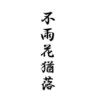

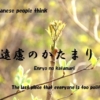
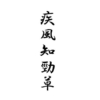

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません