日本再発見 お香の魅力 お勧め3品
東海道に東北道、中央フリーウェイ、国道に県道、熊野古道に街の路地、色んな道があります。日本にはそれ以外に心の中に存在する道があります。柔道、剣道、空手道、華道、茶道に書道です。この道は特定の技術の修行を通じて精神を鍛えることを言います。
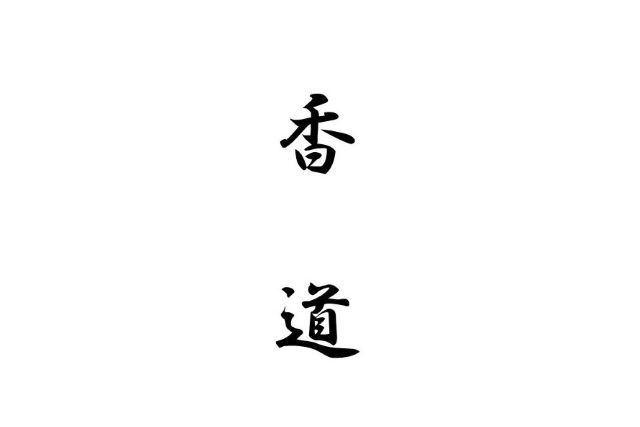
今、柔道や剣道はスポーツです。華道や書道はアートと言われます。スポーツの練習はテクニックを上達させるためにやるんだ、試合に勝てばよい。アートは人気が出るのが大切だ。それ以外に何が必要なんだ。これが世界の標準的な考え方でしょう。ですが日本人はそれだけでは物足りないのです。せっかく厳しい修行をするのだから精神も一緒に鍛えて立派な人になろうと考えます。欲張りなんですね。

お香の歴史
そんな道の一つに「香道」があります。仏教の儀式で使うお香はお線香と呼ばれます。蚊取り線香もその仲間です。一般的にお香と呼ばれるものは香りを楽しむものです。その楽しみ方を体系化したのが香道です。香道は華道や茶道ほど知られていませんが、歴史はたいへんに古く平安時代にまで遡ります。平安時代は西暦794年から1185年までの貴族が政治を行った時代です。源氏物語を書いた紫式部や枕草子の清少納言など女性作家が活躍した時代でもあります。
お香は飛鳥時代の538年に中国から仏教と共に仏前を清める供香として伝来しました。奈良時代の753年、鑑真和上が唐からやって来ます。鑑真和上は仏教の戒律とたくさんの香薬と配合を持ってきました。貴族たちはそのお香を唐風の教養として学びました。
彼らはお香を仏教儀式に使うだけでなく日常生活でを楽しむようになります。香料を複雑に練り合わせて「薫物」を作って香りを楽しんだり、香炉で燻らして香りを着物に移す「移香」を楽しみました。その姿は源氏物語や枕草子にも度々描かれています。

香木のこと
香木は東南アジアで採られる良い香りの木です。日本の最も古い香木の記録は日本書紀にあります。西暦595年淡路島に大きな香木が打ち上げられました。東南アジアから黒潮に乗って日本に流れ着いたのでしょう。島人が香木と知らずに、薪と一緒にかまどで燃やすとたくさんの煙と良い香りが遠くまで広がりました。島人は不思議な事としてその木を朝廷に献上しました。その香木は沈水香木(じんすいこうぼく、沈香)だったと言われています。日本で一番有名な香木、正倉院にある「蘭奢待」も沈水香木です。
沈水香木はジンチョウゲ科のアキラリア属やゴニスチラス属の樹木からできる香木です。それらの木は病気や傷を受けると防御反応として樹脂を分泌します。その樹脂が細菌やバクテリアによって数十年から数百年をかけて変質・熟成されると香りの元になります。最高級の伽羅は樹脂の含有量が5割を超えます。
香木はこのような偶然を積み重ねて出来るのでたいへんに貴重です。生産国にとっては重要な輸出品です。そのため乱獲され今はあまり採れなくなっています。その希少価値は一攫千金を狙う香木ハンターが現れることでも分かります。今後も益々貴重になるだろう香木を使った香道とはどのようなものでしょう。

香道とは
平安時代の次は武士が政治を行う鎌倉時代です。武士は内省的な禅宗を好み、その影響を受けてお香の楽しみ方も一本の香木の香りを極める精神性を重視するようになります。香木の香りをより繊細に鑑賞しようとしました。単にお香を鼻で嗅ぐのではなく精神を集中して香りの奥深さを味合うのです。その行為をお香の香りを聞くとして、「聞香」と呼びました。その作法がこの時代に確立されます。
「聞香」は室町時代に日本独自の文化として花開きます。茶の湯(茶道)や生け花(華道)と同じように新しい文化として更に進化しました。江戸時代になると貴族や武士だけでなく裕福な町人にも香の文化が広がります。「組香」が創作され優れた香道具が作られました。香を鑑賞するための種々の作法が整えられ「香道」として確立されました。
香道は簡単にいうと、お香を燻らせてそのお香がどこで採れた香木かを当てる儀式です。香道に多くの流派があり作法はそれぞれ異なりますが、稀少な天然香木を研ぎ澄まされた感性で判別するという世界感は共通しています。儀式は聞香炉の灰を整え、火種の上に銀葉と言われる雲母片を乗せ、その上に香木を置いて燻らせます。その参加者は回される聞香炉の香を聞き種類を紙に書いて挺出する、という風に進みます。その種類は六国という香木の原産地と五味という香りの風味の組み合わせで表現されます。ちなみに六国は次の通りです。
伽羅 (きゃら)ベトナムの限られた地域に産する最高級の沈香。
羅国 (らこく)タイで取られた沈香。
真南蛮 (まなばん)ベトナム産の沈香。
真那伽 (まなか)マラッカ経由で渡来した香木。
佐曽羅 (さそら)地名説他、諸説がある沈香。白檀を使う流派もある。
寸聞多羅(すもたら)スマトラ島産出の沈香。
マラッカが真那伽、スマトラが寸聞多羅とか、どれも歴史の浪漫が感じられる名前です。5味は、酸、苦、辛、甘、鹹(かん、塩辛い)のことです。これを組み合わせて酸苦甘というように表現します。六国と五味の組み合わせで61種名香を定められています。香名・法隆寺、国・佐曾羅、五味・酸苦甘という風です。香を聞いて、この61種から当てるのですから集中力と経験が必要になります。

日本のお香、お勧めの3品
香木は高価になりましたが、近代は人工合成香料が開発されて色んな香りを楽しめます。お香も花の香りや森の香り、清々しい香りや甘い香りなど今まで無かった香りのもががあります。お香は部屋の邪気を払い穏やかな気分をもたらします。ただ古に王朝や香道の気分を味わうには、香木を原料にしたものがよいようです。
そんな気分を味合える一つに京都の松栄堂さんの芳輪シリーズがあります。種類は、天平、室町、堀川、元禄、白河、二条の6種類です。そのなかでも。沈香を配合した天平と室町、白檀の堀川がお勧めです。
芳輪 ・天平は、高級沈香の気品の高い和の香り。深みのある自然な残り香が漂います。
芳輪 ・室町 沈香の荘厳な香り。こっくりとしたスパイシーさと穏やかな甘みで、落ち着きのある香りに仕上げました。
芳輪・堀川 白檀のまろやかな甘みが感じられる伝統的な和の香り。濃厚で香ばしく、包み込まれるような温もりのある香りです。
どれも、平安時代の貴族の気分、香道を嗜む気分が味わえます。
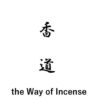

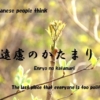




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません